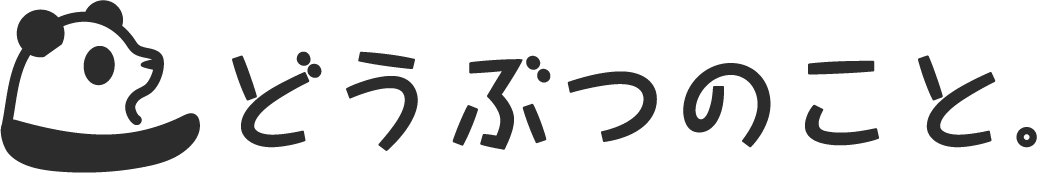日本には、先祖や亡くなった大切な存在を思い出し、供養する「お盆」という文化があります。
お墓参りや迎え火・送り火などの行事が知られていますが、実はこの時期に“動物たち”が登場する風習や信仰があることをご存知でしょうか?
たとえば、きゅうりやなすで作る「精霊馬」や「精霊牛」、魂の化身とされるホタル、そして近年では家族としてともに暮らしたペットたちの供養も注目されています。
本記事では、日本各地に伝わる「お盆・慰霊と動物」にまつわる文化や伝承を、ご紹介していきます。
馬と牛(精霊馬・精霊牛)|ご先祖の乗り物としての象徴

精霊馬・精霊牛とは?

お盆の時期になると、きゅうりとなすに割りばしやつまようじを刺して作った小さな馬や牛の飾りを見かけることがあります。
これは「精霊馬(しょうりょううま)」と「精霊牛(しょうりょううし)」と呼ばれ、ご先祖様の霊がこの世に帰ってくるため、またあの世へ戻っていくための“乗り物”として用意されるものです。
- 精霊馬(きゅうりの馬): 足の速い馬に見立てて、ご先祖様が一刻も早く家に帰ってこられるようにという願いが込められています。
- 精霊牛(なすの牛): 足の遅い牛に見立てて、帰り道はゆっくりと、供物を載せて持ち帰ってもらいたいという思いが込められています。
精霊馬・精霊牛は「迎え火」「送り火」と並ぶ、お盆の大切な供養・迎え入れの風習の一つです。
精霊馬が象徴するもの
精霊馬や精霊牛は、「迎え火」「送り火」と並ぶお盆の三大風習の一つともいわれています。
単なる飾りではなく、故人の霊を想い、家族が心を込めて作る供養のかたちです。
子どもと一緒に作る家庭も多く、手作りを通して命のつながりを学ぶ機会にもなっています。
歴史と地域ごとの違い
この風習の起源は、平安時代の貴族文化にまでさかのぼるとされており、当時は供物や儀式の一環として行われていました。
江戸時代に入ると庶民の間にも広がり、今では日本各地で親しまれる行事となっています。
精霊馬に込められた想い
きゅうりやなすに足をつけたその素朴な姿には、「また会えたね」「来てくれてありがとう」「気をつけて帰ってね」といった、ご先祖様へのやさしい気持ちが込められています。
精霊馬は、古くから続く供養のかたちでありながら、現代の家庭にも静かに息づく「心の乗り物」。
ホタル|死者の魂と重なる小さな光

お盆とホタルの不思議なつながり
夏の夜をやさしく照らすホタルの光。
その幻想的な姿は、昔から日本人の心に深く寄り添ってきました。特にお盆の時期には、ホタルを「死者の魂が姿を変えたもの」として見る民間信仰が各地に伝えられています。
ホタルが多く飛び交う初夏からお盆にかけての季節。
この時期の自然現象と、祖霊を迎えるという日本の精神文化が重なり、ホタルは「魂の象徴」として、慰霊や供養の心とともに語られるようになりました。
魂の化身としてのホタル

例えば…
- 広島県安芸高田市: 広島県安芸高田市の満能のホタルは毛利方と尼子方の戦いで亡くなった兵の魂
- 静岡県浜松市: の八幡螢は武田と徳川の三方原の戦いで亡くなった兵の魂
民間伝承では、次のような解釈が多く見られます。
- 亡くなった家族がホタルとなって帰ってきた
- 戦で命を落とした兵士の魂がホタルの光になった
- 水難事故で亡くなった母子がホタルの姿となって夜空をさまよっている
こうした物語は、ホタルのはかない命や、淡く光る様子が“あの世とこの世をつなぐ存在”として人々の心に響いてきた証といえるでしょう。
ホタルを見かけたとき、「これはきっと誰かが会いに来てくれたんだ」と思う気持ちは、現代でも多くの人々に共感されています。
ホタルが教えてくれること
ホタルの短い命や静かな光には、「死を悼む気持ち」や「魂の再会」への希望が込められています。
お盆の夜にふと目にするホタルは、ただの昆虫ではなく、私たちの心の奥深くに触れる存在なのかもしれません。
ホタルは、命の循環と、亡き人への想いをそっと伝えてくれる、小さな光のメッセンジャーです。
猫や犬|家族の一員としての現代的な供養
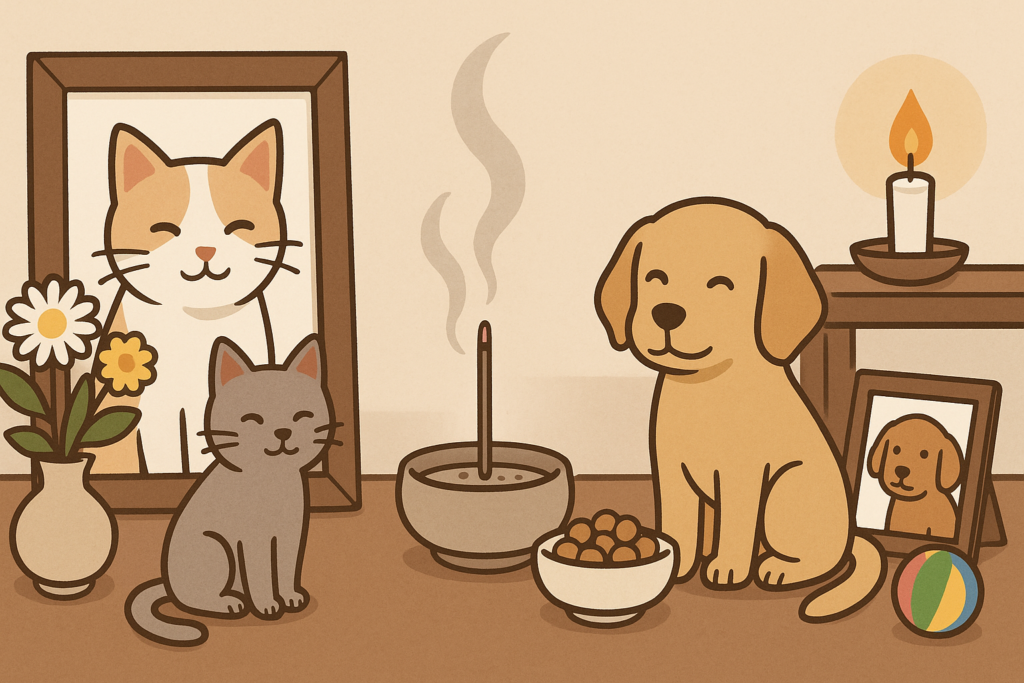
わたしの愛猫も1年ほど前に闘病の末亡くなりました。亡くなってしばらくの間、不思議な現象が続き、「ああ、いるんだな」と確信しました。
ペットも「お盆に帰ってくる存在」へ

近年、猫や犬と暮らす家庭が増え、彼らは“ペット”という枠を超えて、大切な「家族の一員」として見なされるようになってきました。
それに伴い、お盆の時期に亡きペットたちの魂を迎え、感謝と想いを伝える「ペット供養」の文化も少しずつ広がりを見せています。
仏壇の隣にペット専用の小さな祭壇を設けたり、おやつやお気に入りだったおもちゃを供えたりするご家庭も少なくありません。
「今年も帰ってきてくれたかな」と静かに語りかける姿は、人間のご先祖様を迎えるのとなんら変わりのない、あたたかな祈りの形です。
現代のペット供養文化とは別に、昔から日本には猫や犬にまつわる「霊的な存在」としての言い伝えもありました。
猫に関する迷信・伝承

「猫が棺をまたぐと、死者が成仏できない」といった迷信は、広島や長崎など全国で語り継がれています
猫が霊を呼び寄せる、あるいは霊が猫に宿るという考えも見られ、どこか神秘的で境界的な存在とされているのですね。
参考:国際日本文化研究センター
犬に関する信仰・風習

- 長野や秋田など、山岳信仰の残る地域では、山犬(ヤマイヌ)=オオカミが死者の魂を導く存在として信じられてきました。
- 埼玉県の三峯神社では、神の使いとして「オオカミ(大口真神)」が祀られています。「オオカミ」は、魔除け・火伏せ・盗賊除けなどの守護、そして集落や人々の霊を見守る神聖な象徴とされています。
- 山犬札(お札)を授かり、家や田畑・店舗の守護・除災招福を祈願
これらの伝承は、人間と動物との深い関係性や、目に見えないものへの畏れ、敬意のあらわれともいえるでしょう。
ペット供養の広がりと形
動物専用の霊園や供養寺院も多く見られるようになりました。

お盆やお彼岸の時期には、「ペット合同慰霊祭」や「お盆法要」が開催され、動物たちに手を合わせる飼い主さんの姿が見られます。
供養の方法も多様化しており、以下のようなスタイルがあります:
- 仏壇の一角にペット用のスペースを設ける
- ペット霊園や動物寺院で合同法要に参加する
- SNSでメモリアル投稿をする(#虹の橋 など)
- 精霊馬の横にペットの写真や好物を一緒に飾る
こうした供養の仕方は宗教的な決まりにとらわれず、個人の想いやライフスタイルに合わせて自由に行われているのが特徴です。
亡き動物たちへの祈りは、いまも続いている

私たちが共に暮らした猫や犬は、かけがえのない存在であり、命の記憶です。
彼らに対して「また会いたい」「ありがとう」という想いを込めて手を合わせています。お盆の季節に、そっと帰ってきてくれるあの子たちの気配を感じながら、静かなひとときを過ごしています。
トンボ|ご先祖が姿を変えて訪れると言われる風物詩

お盆の空に舞う「盆トンボ」
夏の終わり、青空の下をスッと飛ぶトンボの姿に、ふと懐かしさや郷愁を覚える人も多いのではないでしょうか。
日本のいくつかの地域では、この季節に現れるトンボを「盆トンボ」または「精霊トンボ」と呼び、ご先祖様が姿を変えて会いに来てくれたのだと信じられてきました。
特に中部地方や東北地方を中心に残されており、トンボが人のまわりを飛ぶ様子を「祖霊が見守っている証」として、子どもたちにも語り継いでいます。
特にお盆時期の虫(トンボ・蝶など)=精霊という考えや、その虫を「捕まえてはいけない」という慣習は、多くの地域で祖霊信仰と一体となっています。
トンボに込められた意味と信仰

トンボは、昔から「勝ち虫」として縁起のよい存在とされてきましたが、お盆の時期にはそれとは別の意味が加わります。
先祖の魂が一時的にこの世へ戻り、家族の元を訪れる。その“乗り物”や“化身”として、儚くも自在に空を舞うトンボは、まさにその象徴だったのです。
- トンボが自宅の周囲に現れたら、先祖が帰ってきた合図
- 赤とんぼは、秋の訪れとともに霊の帰還を知らせる存在
- 小さな子どもの肩に止まるのは、先祖がそっと守っている証
各地で「赤とんぼ」や「トンボ」がご先祖様や祖霊の象徴、迎え火、送り火代わりとして意識されてきたことには、文献・民俗学的調査が裏付けています。
トンボが運んでくれる心の風景
トンボの羽音はとても小さく、空を舞う姿もあっという間に視界から消えてしまいます。
だからこそ、ほんのひとときでもその存在を感じたとき、人は「誰かが来てくれた」と感じ、そっと手を合わせたくなるのかもしれません。
この季節、ふいに目の前を横切るトンボに気づいたとき、「おかえりなさい」「会いに来てくれてありがとう」――そんな気持ちを込めて、空を見上げてみてはいかがでしょうか。
地域と信仰の違いについて
日本に伝わるお盆や慰霊にまつわる風習は、共通する部分も多くありますが、その背景にある信仰や表現方法には地域ごとの違いが色濃く表れています。
「精霊馬・精霊牛」は全国的に広く知られていますが、使われる素材や飾り方、飾る場所などには地域性が見られます。
一方で、ホタルやトンボを“霊の化身”とみなす文化は、主に自然と密接に関わる暮らしを営んできた山間部や農村地域に多く、口承で受け継がれてきたものが中心です。
猫や犬に対する信仰や迷信は、その地域の民話や風習、さらには時代背景にも影響を受けています。
現代では「ペット供養」という新しい形が加わり、宗教を問わず、故動物への祈りを表現する方法がより柔軟で個人的なものへと変化しています。
こうした違いは、単なる風習の差ではなく、「命をどう捉え、どう見送るか」という地域ごとの価値観や、自然とともに生きる暮らしの知恵が息づいている証でもあります。
お盆や慰霊に関係する動物とその象徴まとめ
| 動物 | 象徴・意味 | 伝承・出典例(地域) |
|---|---|---|
| 馬・牛 | ご先祖の乗り物、供養のシンボル | 全国/江戸時代以降に普及、精霊馬文化 |
| ホタル | 魂の化身、戦没者や水死者の霊 | 広島県安芸高田市、静岡県浜松市ほか |
| 猫・犬 | 守護、魂の導き、家族の一員 | 猫の迷信(京都・広島)、山犬信仰(三峯神社等) |
| トンボ | 先祖の霊の象徴、盆トンボ | 長野・山形・秋田など東北・中部地方 |
おわりに
お盆という行事は、亡き人を思い、静かに心を寄せる大切な時間です。
動物たちはさまざまなかたちで登場し、時には乗り物として、時には魂の象徴として、そして近年では家族として、供養の場に寄り添ってきました。目には見えないけれど、確かに感じられる「つながり」。
トンボの羽音、ホタルの光、そして精霊馬の足音は、いずれも私たちの心にある“記憶と祈り”をやさしく呼び起こしてくれます。
今年のお盆は、自然の中にふと現れる動物たちの姿に、少しだけ耳を傾けてみてはいかがでしょうか。
そこには、きっと大切な誰かの気配がそっと寄り添っているかもしれません。
関連記事
この記事の執筆者 / 監修者

-
動物専門・ペット特化のWebライター・ディレクター・デザイナー。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、大手企業で広報や編集校正の仕事を経て、猫専門ペットホテル猫専門ペットホテル・キャッツカールトン横浜代表、動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。
幼少期から犬やリス、うさぎ、鳥、金魚など、さまざまな動物と共に過ごし、現在は4匹の猫たちと暮らしています。デザインと言葉で動物の魅力を発信し、保護活動にもつなげていきたいと思っています。
 動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える
動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える 2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説
2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説 動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介
動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介 2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】
2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】