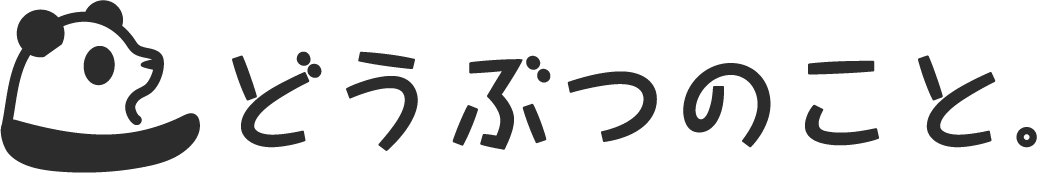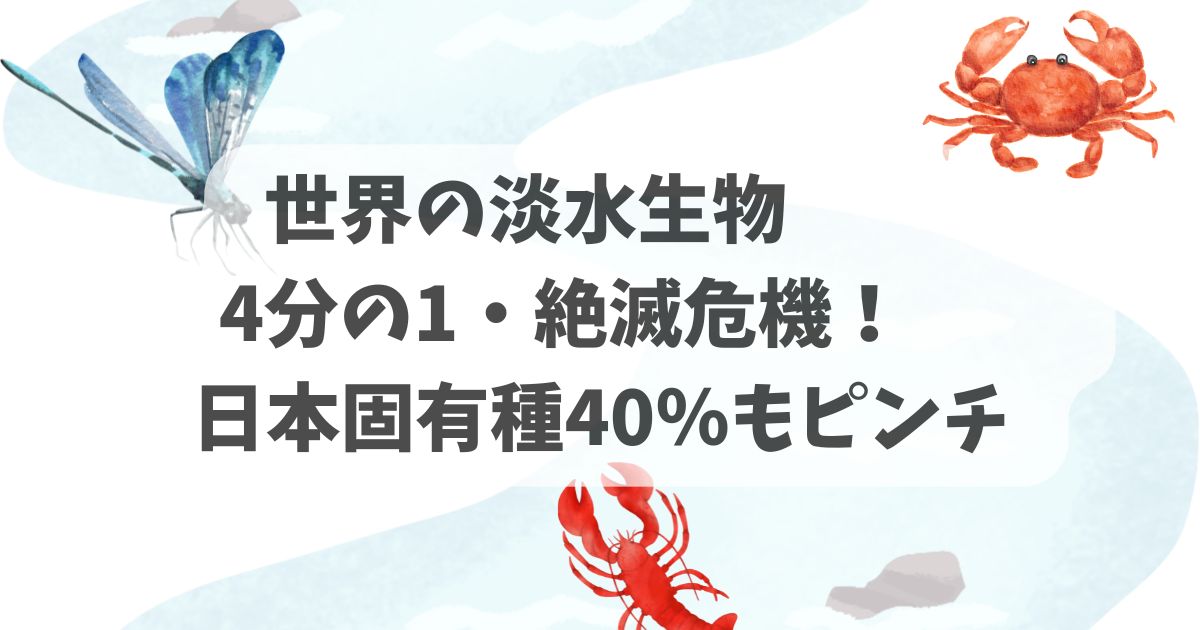目次
地球規模で明らかになった淡水生物・約4分の1が絶滅の危機

淡水に住む生物の約4分の1が絶滅の危機にあることが判明しました。国際自然保護連合(IUCN)が行った調査は名城大学の谷口義則教授も参加し、2025年1月に国際科学誌「Nature」に掲載されました。
- 調査対象:淡水魚、エビ・カニ、トンボなど23,496種
- 絶滅危機種の割合:24%
- 魚類:26%
- エビ・カニ類:30%
- トンボ類:16%
- 過去に絶滅した種:1500年以降で89種
分布や生態が詳しく分かっていない種が多く、実際の危機はさらに深刻であると推測されています。
日本固有の淡水魚も40%が絶滅の危機に

IUCNの調査結果に加え、日本独自の淡水魚も厳しい状況にあります。環境省が発表した「レッドリスト2020」によると、日本固有種の約40%が絶滅危惧種に分類されています。
- 評価対象:約400種
- 絶滅危惧種:167種(全体の43%)
これらの魚は川や湖、湿地などに生息しており、人間の活動による影響を大きく受けています。
絶滅の主な4つの原因

1. 生息地の破壊
川や湿地が都市開発や農地拡大で失われています。特に昔ながらの水田に住む生物は影響を受けやすいです。
2. 外来種の侵入
ブラックバスやブルーギルといった外来種が、固有種を捕食したり、生存競争に勝ったりすることで生態系が乱れています。
3. 水質の悪化
農業や工業による排水が、川や湖を汚染しています。
4. 過剰な漁業
観賞用や食用目的で魚が乱獲され、数が減少しているのです。
私たちができること
淡水生物を守るために、個人や地域でできることもあります。
- 外来種を捨てない:観賞魚や外来種を自然に放すことは禁物です。
- 川や湖の清掃活動に参加する:地域の自然を守る活動が、身近な生物の保護につながります。
- 淡水生物について知る:危機的状況を学び、多くの人に伝えることが保護の第一歩です。
淡水生物を守ることは、私たちの未来を守ること
淡水生物は地球環境の健康を支える重要な存在です。
特に日本固有種は、私たちの文化や自然環境の豊かさを象徴しています。このままでは取り返しがつかない危機を迎える可能性があります。
数字が示す現状をきっかけに、自然を守る行動を始めてみませんか?
この記事の執筆者 / 監修者

-
動物専門・ペット特化のWebライター・ディレクター・デザイナー。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、大手企業で広報や編集校正の仕事を経て、猫専門ペットホテル猫専門ペットホテル・キャッツカールトン横浜代表、動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。
幼少期から犬やリス、うさぎ、鳥、金魚など、さまざまな動物と共に過ごし、現在は4匹の猫たちと暮らしています。デザインと言葉で動物の魅力を発信し、保護活動にもつなげていきたいと思っています。
 2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える
2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える 2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説
2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説 動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介
動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介 2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え
2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え