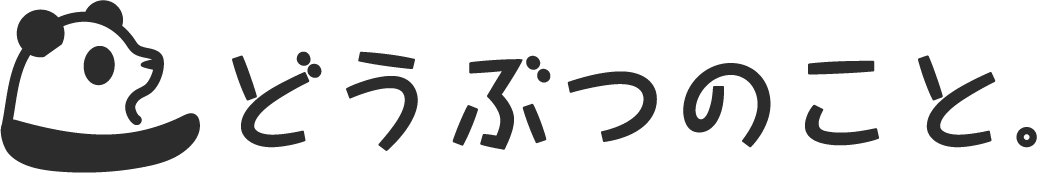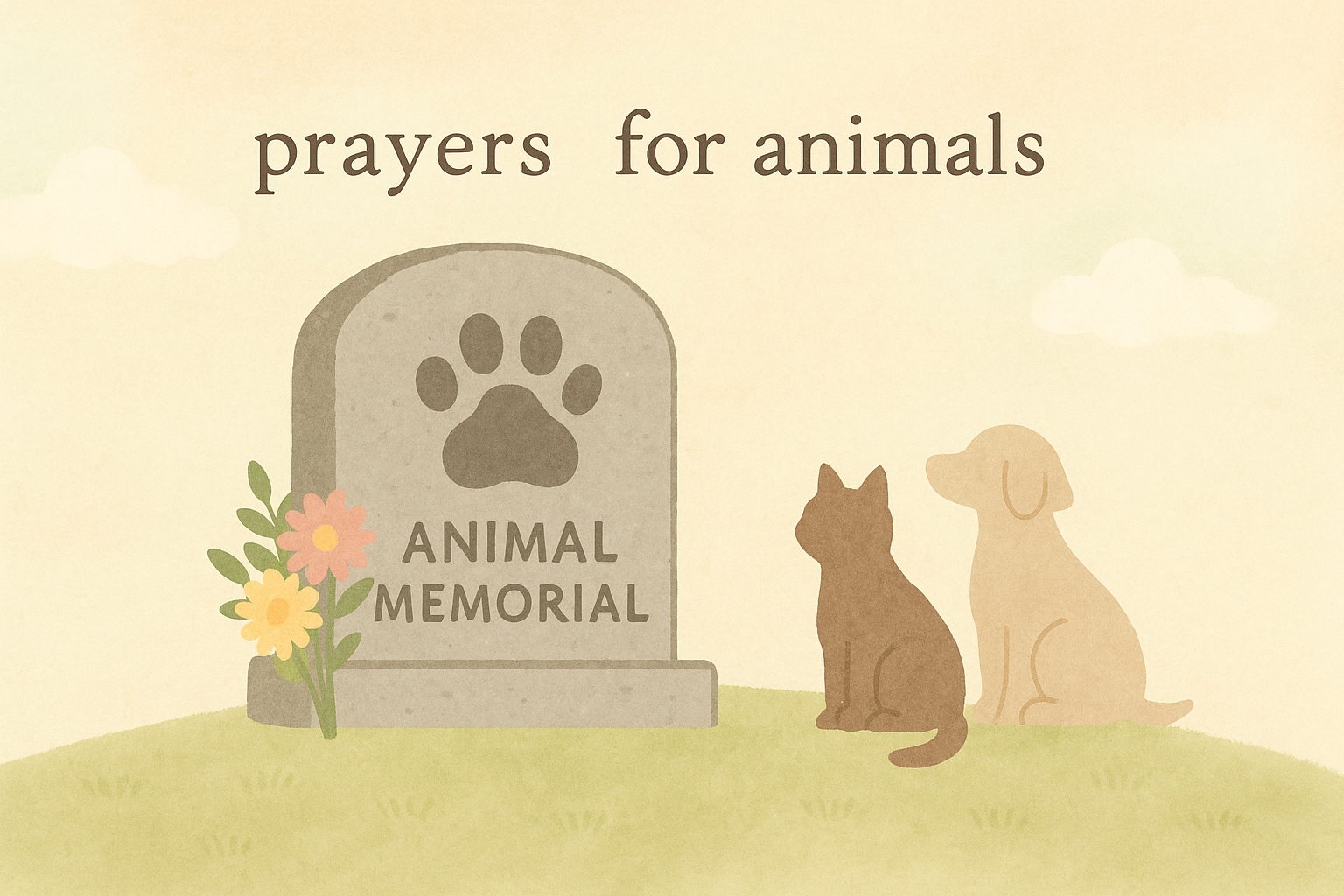はじめに|全国にある「動物のお墓」や「供養の場」
わたしたちの身のまわりには、昔からたくさんの動物たちがいて、暮らしを支えてくれたり、心を癒してくれたりしてきました。田畑を耕す馬や牛、狩りや見張りをしてくれる犬、蚕(かいこ)や蜂、そして今では家族のような存在になったペットたちも。
日本では、こうした動物たちに対して「ありがとう」の気持ちを伝えるために、お墓をつくったり、お祈りをしたり、慰霊碑を建てたりする文化が昔から根づいています。ときには村のお祭りになっていたり、神社やお寺に動物のための碑があったり。
それは、外国にはあまり見られない文化で、「命あるものすべてに意味がある」という、日本独特のやさしい考え方に支えられてきたものです。
この記事では、そんな日本各地にある動物や生きものたちへの供養・慰霊について、やさしく・わかりやすくご紹介していきます。
【熊】クマの霊送り儀礼・イヨマンテ…命に感謝して

動植物、自然現象、生活道具などさまざまなものに魂が宿っているとアイヌ民族は考えてきました。
中でも、アイヌ(人間)にとって重要な働きをするもの、強い影響力があるものをカムイと呼んで尊敬します。アイヌ文化では、クマは「キムンカムイ」と考えられ、特別な存在として敬われています。
イヨマンテで盛大かつ厳粛な饗宴を行い、たくさんのお土産を持たせて仔グマの魂を送ることで、その再訪を願うという、アイヌ民族にとって最も重要な儀礼のひとつです。
こちらは国立アイヌ民族博物館を取材したときの記事です。命について考えさせられます。↓

【猫】恩返しで有名?「猫塚」のお話(東京・大阪など)
猫に関するお話は、日本各地にたくさん残っています。とくに有名なのが「恩返し」の伝説。昔の人々は、病気を治してくれたり、家を守ってくれたりした猫を「神さまのようにありがたい存在」と考えていました。
そんな猫たちに感謝の気持ちを伝えるために作られたのが「猫塚(ねこづか)」です。
【東京・豪徳寺】招き猫のモデル・猫の供養塔
たとえば東京の豪徳寺には、招き猫のモデルになったと言われる猫の供養塔があり、多くの人が手を合わせに訪れます。
#猫好きさんと繋がりたい#井伊家 の墓所で、#招き猫 発祥の地とも言われる『豪徳寺』。
— 秋ゑびす(旅ネタ専門) (@yamashita99) November 24, 2019
【幸福を招く】ことを祈って多くの人が招き猫を奉納されますが、参拝さんの会話を聴くと、中には『亡くなった飼い猫』の供養の為にくる方も居られるようです。
<東京都 世田谷区、豪徳寺駅最寄> pic.twitter.com/sULOqEYlYm
忠猫神社
— VelludoRain (@VelludoRain) May 24, 2023
主祭神は忠猫ニケ
1895年、伊勢多右衛門は凶作で困窮する民衆を救うため米蔵を解放したが大量の鼠が襲う。⁰すると多右衛門の飼猫ニケが狼の如く鼠を撃退。
また多右衛門が私財を投じ造成を始めた浅舞公園内の鼠などの害獣も退治。
ニケが13歳で亡くなると顕彰のために碑を建て敬ったと謂う pic.twitter.com/KWTBz6f748
【秋田・忠猫神社】ネズミから米倉を守った飼い猫の功績を称える
秋田県横手市の浅舞八幡神社には「忠猫神社」があり、ご神体は明治期に建てられた忠猫碑です。米蔵をネズミから守った飼い猫の功績をたたえるもので、地元では今も「恩義を忘れない猫」として語り継がれています。毎月22日には“にゃんにゃんの日”として健康祈願や供養祭が行われ、全国から愛猫家が参拝に訪れる人気の場所になっています。
忠猫神社
— penpen (@lookfor7030) May 2, 2025
秋田県横手市平鹿町浅舞蒋沼
猫まみれの無人神社。
引き戸を開けた瞬間、
無数の猫が視界に入り少しビビる!
御朱印や御守り、おみくじも🐈 pic.twitter.com/ozkB8zZn4n
【大阪・松の木大明神】…三味線に使われた猫のための供養
大阪の西成区・松の木大明神には、三味線に使われた猫のための塚があります。
大阪は飛田の路地裏にある松乃木大明神に祀られているのは、猫塚。飛田の芸者が嗜む三味線を作るために屠られた猫を弔うため……らしいけど、猫塚は三味線の形をしている。三味線になる前の形のほうが、愛らしくてよいと思うぞ。 pic.twitter.com/RUa2itAD6o
— 村田らむ (@rumrumrumrum) February 20, 2023
今では考えられない背景ですね。
【犬】忠犬ハチ公だけじゃない!全国にある犬の慰霊碑
犬と人とのつながりは、とても古く、そして深いものです。番犬として家を守ったり、狩りや牧畜の手伝いをしたり、近年では盲導犬や警察犬として人を支える役目も担ってきました。
そんな中で、亡くなった犬たちを悼み、その働きに感謝するために建てられた「犬塚(いぬづか)」や「忠犬塚(ちゅうけんづか)」が、全国にいくつも存在しています。
【忠犬ハチ公】世界一有名な忠犬は渋谷の待ち合わせ場所に
有名な例が、東京・渋谷駅前にある忠犬ハチ公像。ご主人を待ち続けた忠義の姿は、今も多くの人の心に残っています。
おはようございます
— へいてん (@heitenkun) July 31, 2025
本日は楽園渋谷道玄坂店さんへ朝から入店入店!
ハチ公さんは外国の方々に人気でした
えいえい#楽園渋谷道玄坂店#PR pic.twitter.com/TiXIHVv97o
【本日開館!】
— 渋谷区立松濤美術館【公式】 (@shoto_museum) July 21, 2025
安藤照が制作した初代《忠犬ハチ公像》は、狛犬の形を参考にして作られたそう。これを証言したのは、安藤の親友で洋画家の谷口午二でした。後に谷口は、二人の故郷の鹿児島市立美術館の初代館長となります。本展では、谷口旧蔵のテラコッタ製の小型《忠犬ハチ公像》を展示中です。 pic.twitter.com/qcCBBDtVfG
【静岡・光前寺】霊犬早太郎の民話
また、静岡県の光前寺に伝わる「霊犬早太郎」など、民話の中で語り継がれてきた忠犬の物語も少なくありません。
こちらは長野県駒ヶ根市の光前寺にある霊犬・早太郎のお墓。
— 江藤学 (@etoogaku) September 19, 2023
早太郎は同寺で飼われていた山犬で、遠州見付村の人々を苦しめる怪物(老狒々)を命がけで退治したという伝説がある。
そのことから早太郎は不動明王の化身と言われ、災難除けの霊犬として厚く信仰されているそうな。 pic.twitter.com/0D2AM154Yz

【警察犬・災害救助犬・麻薬探知犬】人の命を守る犬たち
警察犬・災害救助犬・麻薬探知犬など、実際に人の命を守る仕事をした犬たちの慰霊碑があり、関係者によって毎年慰霊祭が行われています。
令和6年広報用写真コンクール入賞作品を紹介
— 警察庁 (@NPA_KOHO) February 7, 2025
○ 警察庁長官官房長賞「思いをつなぐ」
長野県警察鑑識課員による作品です。
職務に邁進して功績を残した先輩を弔うきもちは、ひとも犬もおなじだとおもいたい。
警察犬は、今日も警察官と息を合わせて走ります。 pic.twitter.com/2k0k59ErzT
麻薬探知犬の慰霊碑
11月1日は、犬の日。麻薬探知犬訓練センターで、慰霊祭を行いました。センター内の犬魂碑に眠る、数々の摘発を行った麻薬探知犬の功績をたたえ、冥福を祈り、黙とう・献花を行いました。先輩達の密輸摘発への熱い想いはボク達が引き継ぐワン! #犬 pic.twitter.com/lQbTLR3e
— カスタム君 (@Custom_kun) November 1, 2011
犬は、単なるペット以上の存在。人とともに生き、尽くしてくれた命への敬意が、慰霊碑というかたちになって今に伝えられています。
【鯨】命をいただいた感謝を込めて(和歌山・山口・長崎など)
日本の海辺の町、とくに和歌山県や山口県、長崎県などでは、昔から「捕鯨(ほげい)」が盛んに行われてきました。クジラは肉だけでなく、油や骨、ひげなど、体のすべてが無駄なく使われてきた、まさに「恵みの命」だったのです。
でも、その命を奪うという行為に、ただの仕事以上の思いを重ねていたのが日本人の心。だからこそ、クジラに対して感謝と哀悼の気持ちをこめて、「鯨塚(くじらづか)」が各地に建てられました。
【和歌山・鯨供養碑】捕鯨の町の慰霊
たとえば、和歌山県太地町には「鯨供養碑」があり、毎年「鯨供養祭」も行われています。

この鯨碑は1798年、品川沖の漁師たちに捉えられた鯨で、体調16.5mの大きなもの。東京では唯一。

【山口・青海島鯨墓】鯨の胎児が埋葬される
鯨塚・鯨碑は全国にあり、例えば山口県長門市にある鯨塚には、200年以上にわたる鯨の胎児70が埋葬されています。

「命をいただいたことに感謝し、供養する」。それは食文化の根本にある、日本人らしいやさしい祈りの姿かもしれません。
【馬】農耕と運搬を支えた働き者(東北・北海道など)
人々の暮らしがまだ機械に頼っていなかった時代、馬はとても重要な働き手でした。田畑を耕したり、重い荷物を運んだり、ときには人を乗せて遠くまで移動したり。とくに東北地方や北海道のような広大な土地では、馬はなくてはならない存在でした。
そんな馬たちに感謝の気持ちを伝えるために、「馬塚(うまづか)」や「馬頭観音(ばとうかんのん)」と呼ばれる石碑が多く建てられました。馬頭観音は、仏教に登場する馬の守り神で、「馬の魂を慰める」と信じられています。
JR梁川駅北側の、山中に続く階段の先にある彦田観音堂(大月市梁川町)。
— Ing (@ing570) March 12, 2021
灯篭に「献燈馬頭観音」と刻まれているため、本尊は馬頭観音の様子。
そのほか、武士(武田勝頼?)の馬を埋めた伝えがある馬塚をはじめ、オンマラサマ、オシラサマなど情報量が多い。 pic.twitter.com/xqiQnPa2pI
道端やお寺の境内、農村の片隅にひっそりと立っていることも多く、今でも地元の人がお花を供えたり、お参りしたりしている姿が見られます。
岡山競馬場跡地、現在は民間企業の敷地と運動場となっている。画像は運動場南にある馬塚と馬頭観音 pic.twitter.com/tJ8llbd0o7
— ぐっきー (@pc98211) July 16, 2022
働いた馬たちは、ただの動物ではなく「家族」であり「仲間」。その命に「ありがとう」と祈る文化が、今も静かに息づいています。
【牛】田んぼも畑も一緒にがんばった牛たち(東北・北陸など)
牛もまた、かつての農村では欠かせない働き手でした。特に水田の多い東北や北陸地方では、田んぼを耕す「耕牛(こうぎゅう)」として活躍し、重い農具を引きながら、農作業を支えてくれました。
牛は力が強く、性格もおだやか。長い年月をともに過ごすうちに、まるで家族のような存在になっていったといわれています。
牛頭観音
— 米子力研究所 (@beishiryoku_Exp) June 1, 2024
牛がちょっと大きい。 pic.twitter.com/GsSCazhzaB
そんな牛たちに感謝の気持ちを込めて、「牛塚(うしづか)」や「牛頭観音(ごずかんのん)」などの慰霊碑が各地に建てられてきました。田んぼのあぜ道や神社の境内に、そっと佇むその姿は、地域の人々のあたたかな思いを今も伝えてくれます。
引用リツイートで焔摩天との習合という説があった
— キャプテン村社 (@CaptMurasha) February 11, 2023
これがあった南房総は酪農が盛んな地域で、そこら中に牛頭観音や牛頭天王、八雲神社があることも無関係ではないかもしれない? pic.twitter.com/oRrxvTnNBt
また、石川県では「石浦神社」で毎年11月に「牛供養祭」が行われています。
命を支え、共に生きた動物たちを大切にする文化は、時代が変わっても受け継がれています。
【その他の動物・生き物たち】豚・イノシシ・鳥・魚・鹿
豚観世音、鶏、イノシシ、鳥、鹿などの供養塔もありますね。
山形市の誓願寺境内に建立された「豚観世音」と刻まれた碑。畜産農家の方が発願した供養碑だ。
— Ayako Kimishima (@kimi_aya_) October 29, 2021
横には「牛頭観音」「馬頭観音」と刻まれた碑が建立されているが、「豚頭観音」にはならなかったみたい。ちなみに鳥の供養碑には「鳥」とだけ刻まれている。 pic.twitter.com/8WCk3FucaK
馬頭観音・牛頭観音・豚観世音 pic.twitter.com/zTm6XxsIju
— リンク (@Link_dqx) April 11, 2021
【魚】食や研究でお世話になった魚にも感謝の気持ちを
奈良市 釣り堀跡のお魚供養塔
— 兎天良(とてら) (@26_N_1288) August 1, 2023
平城宮跡の西側、亀の井ホテル(旧かんぽの宿)南隣の釣り堀跡にあります。今はカモや鵜、カメさんたちの楽園です。 pic.twitter.com/lF5J3oYGnp
【鵜(う)】岐阜・長良川の「うかい」と鵜塚
岐阜県を流れる長良川では、千年以上の歴史をもつ伝統漁法「鵜飼(うかい)」が今も続いています。鵜飼では、鵜(う)という水鳥を使って鮎(あゆ)などの川魚をとる独特な漁が行われます。
この鵜たちは、「鵜匠(うしょう)」と呼ばれる漁師さんたちと一緒に暮らし、漁の大切なパートナーとして活躍してきました。
そんな鵜たちに感謝し、その命をねぎらうために建てられたのが「鵜塚(うづか)」です。長良川周辺には、鵜のための慰霊碑が点在しており、鵜匠たちは亡くなった鵜を一羽ずつ丁寧に弔い、塚の前で祈りを捧げています。
鵜飼山 遠妙寺 鵜供養塔 pic.twitter.com/M4dCEbp2TW
— かわさんぽ (@kawa_sanpo) July 17, 2017
現代でも、岐阜市では毎年鵜飼終了後の日曜日に鵜供養を行っています。
【鵜供養】
— 長良川うかいミュージアム (@ukaimuseum) October 21, 2024
毎年、鵜飼終了後の日曜日に、鵜飼関係者により鵜の供養が営まれます。
鵜塚での法要のあと、鵜舟から鵜供養を題材に詠んだ短冊を長良川に流します。
今年は4羽の鵜がなくなったそうです。#ぎふ長良川の鵜飼 #ぎふ長良川鵜飼 #長良川 #鵜飼 #鵜飼い #鵜供養 #鵜に感謝 pic.twitter.com/CeGtjWpbIK
ただの“道具”ではなく、“いのちある仲間”として大切にされている——それが、日本の伝統文化に息づく、鵜との関係なのです。
【象や動物園の仲間たち】人を楽しませてくれた動物たちの碑
全国の動物園には、ひっそりと「動物慰霊碑(どうぶついれいひ)」が建てられていることがあります。これは、展示や教育活動のために活躍し、亡くなっていった動物たちを供養するためのものです。
たとえば、上野動物園(東京都)には「動物慰霊碑」があります。毎年9月には職員や関係者によって慰霊祭が開かれています。そこでは、象やライオン、ゴリラ、ペンギンなど、さまざまな動物たちの名前が読み上げられ、感謝と祈りが捧げられます。
動物の慰霊碑 恩賜上野動物園に来たらここも訪問してほしい pic.twitter.com/1dw873AyAT
— カエルーランド (@kaeruland) October 1, 2014
特に象は、人々に親しまれ、記憶に残る存在として語り継がれることが多く、慰霊碑に象の像が添えられている園も少なくありません。
動物たちは、子どもたちに命の大切さや多様性を教えてくれる大切な存在。だからこそ、命が尽きたあとも「ありがとう」「おつかれさま」の気持ちを伝える場が設けられているのです。
それは、展示するだけではない、動物園のやさしいまなざしを感じられる一面かもしれません。
【実験動物】科学発展の陰の存在に祈りを(大学・研究機関)
医学や薬学、生命科学の研究において、多くの実験動物たちが重要な役割を果たしてきました。
【平成30年度医学部動物慰霊祭】
— 大分大学公式 (@OITAuniversity) September 26, 2018
平成30年度大分大学医学部動物慰霊祭が,9月19日晴天の中,実験動物慰霊碑前で行われました。https://t.co/qy7jUiZf6B pic.twitter.com/nqRCY8UQF8
多くの大学では、実験動物慰霊碑が構内にあり、毎年慰霊式も行われます。研究者たちが白衣のまま献花や黙祷を行い、命への敬意を込めて「ありがとう」を伝えるその光景は、静かでありながらとても印象的です。
マウスやラット、ウサギ、カエル、魚類、霊長類など、さまざまな動物たちが、人間の健康や命を守る研究のために使われてきたのです。
#タヌキちゃん命日
— 調布地域猫の会 (@ChofuChiikiNeko) November 4, 2022
府中ペット霊園、慈恵院に着きましたが読経の時間まで、まだ1時間近くあったので、先に合同慰霊碑等へのお参りを済ませました。
学校の飼育動物や実験動物の慰霊碑もあります。タヌキちゃんほか、ここに眠る動物達、人間の犠牲になった動物達のご冥福をお祈りします🙏 pic.twitter.com/Bad8pLJt3X
しかしその一方で、「その命があったからこそ、科学が進んだ」という意識も日本では強く、大学や研究機関には、実験動物のための慰霊碑が多く建てられています。
今日の岩崎さんの話の2番目のテーマは、実験動物慰霊碑、慰霊祭の話。「近代科学の教科書にはオカルティズムは出てこないが、そんな科学の現場に残っているある種のオカルティズム」神主を呼んで慰霊祭をやる研究所も。海外ではあまり例がないらしい。 pic.twitter.com/7QQVxuWlYE
— hanna saito (@0oHANNAo0) June 17, 2015
「科学の進歩の裏には、小さな命があった」
その事実を忘れず、敬意と感謝の気持ちをもって向き合おうとする姿勢が、日本の実験動物慰霊文化には息づいています。
【蚕】人の暮らしを支えた小さな命への祈り
おはようございます♪
— アクセスジョブ熊谷|熊谷市にある就職に強い就労移行支援事業所(在宅支援も充実!) (@aj_kumagaya) June 7, 2022
先日のウォーキングでいった公園にて。
こんな慰霊碑がありました✨
昔、養蚕の産業があったので蚕の慰霊なようですね✨
繭の形をしてます。#就労移行#eラーニング#illustrators #Photoshop pic.twitter.com/9NLSz71cXI
日本では、古くから昆虫たちも人の暮らしに欠かせない存在でした。とくに蚕(かいこ)は、絹をつくるために飼育され、多くの家庭や地域を支えてきました。
シルク岡谷 近代化遺産散歩⑨
— まーくん💙💛@北河内の片隅から (@ko_0021) September 14, 2019
蚕霊供養塔(照光寺内) 1934年 世界恐慌時に製糸業者の発案で広く寄付を募って建立。慰霊祭毎年4/29 本尊馬鳴菩薩坐像。
こんなに立派だと思わず境内を探し回ってしまった(笑)。 pic.twitter.com/0mWObRosC4
明治から昭和にかけては「養蚕」が大きな産業であり、各地に蚕を供養する碑やお堂が残されています。
泉区和泉中央南、蚕御霊神塔。この塔は、慶応2年(1866年)3月の霜害で桑が枯れ、蚕が育たなくなった際、村で多数の蚕を地中に埋葬した悲劇を受け、村人たちがその慰霊のために明治11年(1878年)に建立したものです 。そのうしろには神明神社があります。 pic.twitter.com/QnhzIDEJey
— しまぢ:) (@fujiaoisora) June 15, 2025
【蜂】農業に欠かせない受粉の働き手・はちみつ・ローヤルゼリー
また、蜂も同じように、人間と深く関わってきた昆虫です。蜂蜜やローヤルゼリーを採る養蜂だけでなく、農業に欠かせない受粉の働き手としても重要でした。そのため、養蜂家たちが蜂を供養する習慣もあり、各地に「蜂魂碑(ほうこんひ)」が建てられています。
【イベント情報】栄養・健康食品だけでなく野菜や果物の花粉交配という重要な役割も担っているミツバチの恩恵に感謝して、蜂魂祭(みつばち供養祭)が開催されます。2月8日(水曜日)10時から蜂魂碑前(高松市国分寺町新居)にて http://t.co/PflowqW1 #イベント
— 香川県(広聴広報課) (@PrefKagawa) February 7, 2012
【オケラ】将軍の鷹狩り用の生き餌として
栃木県那須町には「オケラ供養塔」が実在します。これは江戸時代、将軍の鷹狩用の鷹の“生き餌”として大量にオケラ(螻蛄)が農民に採集され、多くの命が失われたことを悼んで建てられたものです。
山形市の誓願寺境内に建立された「豚観世音」と刻まれた碑。畜産農家の方が発願した供養碑だ。
— Ayako Kimishima (@kimi_aya_) October 29, 2021
横には「牛頭観音」「馬頭観音」と刻まれた碑が建立されているが、「豚頭観音」にはならなかったみたい。ちなみに鳥の供養碑には「鳥」とだけ刻まれている。 pic.twitter.com/8WCk3FucaK
この「オケラ供養塔」は、人為的に命を奪われた小さな昆虫にも感謝と慰霊の気持ちを表す、日本らしい生命観や供養文化の象徴的な事例として知られています
こうした昆虫たちは、人にとって「とても小さい存在」でありながら、日々の生活や産業に大きな恵みをもたらしてくれました。お盆や慰霊祭では、「小さな命がどれほど人を支えてきたか」を思い出し、感謝を込めて祈りが捧げられているのです。
【戦争と動物】慰霊の対象となった戦時中の動物たち
お盆や慰霊の話になると、戦争で犠牲になった動物たちの存在も忘れてはなりません。
戦時中、日本では軍馬や軍犬、伝書鳩などが戦地に送られ、人間と同じように命を落としました。戦場で倒れた馬や犬、任務を果たして帰らなかった鳩の姿は、兵士たちにとっても深い記憶として残ったといいます。
愛知県名古屋市東区の建中寺を訪れた。尾張徳川藩の菩提寺、火事や名古屋大空襲からも逃れた種々の江戸期の建物を今でも見ることができる。境内に馬頭観音像が鎮座し、足元に犬と鳩の像を見ることができる。犬は破損したマズルがセメントで丁寧に補修されている。軍用犬や軍用鳩の慰霊碑かもしれない。 pic.twitter.com/mbylQkbQSB
— 杜すいとん 行きたいところばっかし (@wolfmuzzle1) December 27, 2019
戦後、日本各地には「動物慰霊碑」が建てられました。そこには「動物たちもまた戦争の犠牲者である」という強い思いが込められているのです。
https://t.co/IaVf2bsKLU
— 秋ゑびす(旅ネタ専門) (@yamashita99) April 27, 2016
この纏めを読む人にお勧めしたい、戦没した軍馬の慰霊碑。軍用犬と伝書鳩も居ます。
(これは滋賀県彦根市の護国神社の物ですが、東京の靖国神社にも文字だけの慰霊碑が有るそうです) pic.twitter.com/LRI5jiTBZh
お盆の時期には、こうした慰霊碑の前で法要が営まれることもあります。人だけでなく、共に戦い、共に苦しんだ動物たちに祈りを捧げる姿は、「人と動物の絆」がどれほど深いかを物語っています。
【現代に受け継がれる祈り】動物慰霊祭と日常の供養
お盆のある8月は、この1年間に旅立った動物達の慰霊祭でもあり、ねこの吉も、その2700体の中にいます。
— 犬江 八吉 (@byakuyanotabi) August 12, 2023
手を合わせて瞳を閉じると、吉を抱っこしたイメージがふいに現れ、涙が溢れてしまいます🥲
首輪は、まだついていました😺
水をたっぷりかけて、顔と頭、背中をごしごし撫でて、帰りました🍀 pic.twitter.com/H0PqAKkwxZ
現代のお盆や慰霊の場面でも、動物への祈りはしっかりと受け継がれています。ペット霊園や動物霊堂では、毎年お盆の時期に「動物慰霊祭」が開かれ、犬や猫をはじめとする家族同然のペットに手を合わせる人々が集まります。
また、動物園や牧場でも、園や施設で過ごした動物たちに感謝を込めた慰霊祭が行われています。象やキリン、牛や馬など、大型の動物にも「ありがとう」と祈りを捧げる光景はとても印象的です。
こちらは令和6年に亡くなったわたしの愛猫です。月命日には花束を、日々の生活ではお水とフードを置いています。
さらに個人の暮らしの中でも、お盆にペットの写真を飾ったり、お花やおやつをお供えしたりする家庭が増えています。こうした日常的な供養は「大切な命とつながり続けたい」という思いの表れでもあります。
動物たちの魂に寄り添う祈りは、かつての戦争や伝統行事に限らず、現代社会でも変わらず続いているのです。
【まとめ】お盆と動物たちをつなぐ祈りの心
お盆は、人と人だけでなく、人と動物をもつなぐ大切な時間です。
戦争で犠牲になった軍用犬や軍馬、自然の恵みをくれた魚や鳥、そして一緒に暮らしたペットたち。私たちは、お盆を通してその命を思い出し、「ありがとう」という気持ちを新たにします。
動物にまつわる慰霊や供養の習慣は、時代や地域によって形を変えながらも、共通して「命への感謝」を伝えています。送り火や供養祭といった行事は、その象徴的な瞬間でもあります。
お盆に手を合わせるとき、そばにいた動物たちの姿を思い浮かべてみませんか。
その祈りは、過去から未来へとつながる「いのちの橋渡し」になるはずです。
関連記事


この記事の執筆者 / 監修者

-
動物専門・ペット特化のWebライター・ディレクター・デザイナー。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、大手企業で広報や編集校正の仕事を経て、猫専門ペットホテル猫専門ペットホテル・キャッツカールトン横浜代表、動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。
幼少期から犬やリス、うさぎ、鳥、金魚など、さまざまな動物と共に過ごし、現在は4匹の猫たちと暮らしています。デザインと言葉で動物の魅力を発信し、保護活動にもつなげていきたいと思っています。
 動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える
動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える 2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説
2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説 動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介
動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介 2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】
2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】